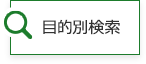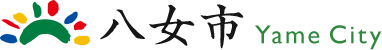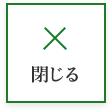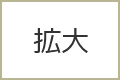障がい福祉サービスの利用方法
対象となる方
-
身体障害者手帳の交付を受けている方
-
療育手帳の交付を受けている方
-
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
-
自立支援医療(精神通院医療)を受給している方
-
難病などのある方
対象となる難病については、下記をご覧ください。
指定難病一覧(令和6年4月1日現在)(PDFファイル:135.6KB)
なお、18歳未満の「障がい児」と認定された人も、児童福祉法に基づき一部サービスを利用することができます。
利用料
利用者は、サービスに掛かった費用の1割を負担します。
ただし、費用負担が重くなりすぎないように、所得の状況に応じて支払う費用の限度額が決められています。なお、提供されるサービスによっては、食費や光熱水費等の実費を負担していただくことがあります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
| 18歳未満の方、施設入所支援・療養介護を利用する20歳未満の方 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
| 18歳以上の障がい者(上記に該当する方を除く) | 本人及び配偶者 |
訪問系サービス(※1)・日中活動系サービス(※2)を利用されている方
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
| 18歳未満 | 18歳以上 | ||
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | 0円 |
| 低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
| 一般1 | 市民税課税世帯で、所得割が16万円(児童は28万円)未満 | 4,600円 | 9,300円 |
| 一般2 | 市民税課税世帯で、一般1以外 | 37,200円 | 37,200円 |
※1訪問系サービス:居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、短期入所
※2日中活動系サービス:生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
居住系サービス・療養介護を利用されている方
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | ||
| 施設入所・療養介護 | グループホーム・宿泊型自立訓練 | |||
| 20歳未満 | 20歳以上 | 18歳以上 | ||
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 一般1 | 20歳未満の施設入所支援、療養介護利用者で、市町村民税の所得割が28万円未満 | 9,300円 | - | ― |
| 一般2 | 市町村民税課税世帯で、一般1以外 | 37,200円 | 37,200円 | 37,200円 |
障がい福祉サービス利用までの流れ
利用希望のサービスによっては、申請からサービス利用までに2ヶ月程度かかります。
初めてサービスの利用を希望される場合は、早めに福祉課障がい者福祉係までご相談ください。
また、障がい福祉サービスには「介護給付サービス」と「訓練等給付サービス」があります。
詳しい内容は、下記の表をご覧ください。
サービスを利用するための基本的な手続きは、以下のとおりです。
| 手順 | 内容(詳細は窓口にてお尋ねください) |
| 1 | 市の担当窓口に申請書を提出します。 |
| 2 | 利用者は利用計画案提出依頼届出書を相談支援事業者に提示し、契約を結んで、利用計画案の作成を依頼します。その後、計画相談支援の事業所が「サービス等利用計画案」等を作成します。 |
|
3 |
【障がい支援区分が必要な方】 認定調査員が、現在の生活や障がいの状況についての調査を行います。 |
| 4 |
【障がい支援区分が必要な方】 公平を期すために、全国統一の調査項目が定められ、コンピューターで判定されます。(一次判定) |
| 5 | 相談支援事業者によって作成された計画案を市に提出します。 |
| 6 | 市では、障がいのある方の心身の状況や介護者の状況のほか、利用計画案を勘案し、支給決定をします。支給決定後は受給者証を交付します。 |
| 7 | 受給者証をサービス事業者に提示し、契約を結んで、サービスを利用します。 |
必要な書類
- 障害福祉サービス等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(PDFファイル:102.2KB)
- 世帯状況・収入申告書・同意書(PDFファイル:101KB)
- 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(PDFファイル:59.7KB)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)受給者証をお持ちの方はその受給者証
- 難病等のある方は、その疾患名が確認できる書類(特定疾患医療受給者証や特定疾患医療登録者証、診断書など)
- 障害年金等の受け取り額がわかるもの(年金改定通知書、年金が振り込まれている預金通帳等)
- 申請者(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
- 健康保険証(療養介護申請のみ必要)
※在宅で就労サービスを利用される場合