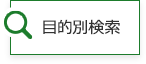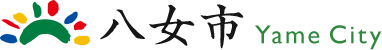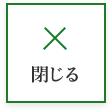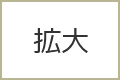八女福島の燈籠人形

八女市本町の福島八幡宮境内で、放生会の奉納行事として秋分の日頃の3日間に公演されます。
山鹿の大宮神社から奉納燈籠をもらい受け、江戸時代半ばに福島町民が独自の工夫をして人形の燈籠を奉納したのが始まりだといわれています。そのころ大阪方面で流行っていた人形浄瑠璃の技術を取り入れて現在の形になりました。3層2階建の釘や鎹を1本も使用しない屋台が、期間中だけ組み立てられ、囃子にあわせてからくり人形芝居が上演されます。

見どころは人形の橋渡し・衣裳の早変わりなど。
冊子『八女福島の燈籠人形(観る・知る・学ぶ、八女は楽しいシリーズ)』
令和7年度公演のお知らせ
「八女福島の燈籠人形」は、江戸時代から約280年の永い間、庶民の手により守り受け継がれ、八女の風土と歴史を反映した誇り高き民俗芸能であります。
公演日
口開け公演:9月20日(土曜日) 20:00~
本公演:9月21日(日曜日)~23日(火曜日)
公演時間
口開け公演 20:00~
本公演:9月21日(日曜日)~23日(火曜日) 13:30 15:00 16:30 19:00 20:30
芸題
春景色筑紫潟名島詣(はるげしきちくしがたなじまもうで)
芸題解説
《ものがたりのあらすじ》
弁財天を厚く信仰する大名一行が従者を引きつれ、筑前・名島神社に詣でました。筑紫の潟は、やわらかな春風が差し込み、帆をあげた小舟はのどかに行き交い、その帆影は春の波間に漂っています。筑紫の国は春たけなわです。門前の茶店で盃を傾けていた大名一行は、春の情景に酔いしれ思わず盃が進み、いつのまにかまどろむのでした・・・。(夢の中・・・、)
衣をまとった舞姫姿の弁財天が側近である十五童子のひとり金財童子を連れだち現れます。愛宕の宮、筥崎八幡、あるいは千代松原・・・。最後に名島の社に舞い降りて周囲に桜吹雪が舞い散るなか弁財天と金財童子は、心ゆくまで社前で舞い遊びました。
演題解説(漫画)
今年の演題である「春景色筑紫潟名島詣」を漫画で分かりやすく解説しています。
八女福島の燈籠人形マンガ解説(春景色筑紫潟名島詣_日本語版)
会場
この記事に関するお問い合わせ先
文化振興課 文化振興係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1982
ファックス:0943-24-4331
お問い合わせはこちら