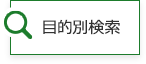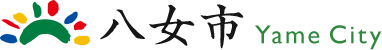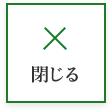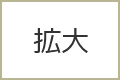市長所信表明(令和6年11月27日)

おはようございます。この度、第10代八女市長に就任いたしました簑原悠太朗でございます。
令和6年第5回八女市議会定例会の開会に際しまして、市長就任後初めての定例会でございますので、貴重な時間を拝借いたしまして、今後の市政運営の基本方針について、所信の一端を述べさせていただきます。
私は、11月10日執行の市長選挙におきまして、多くの市民の皆様からご支持をいただき、市政の運営を担わせていただくこととなりました。この八女市、様々な課題が山積する中、新たな時代に向けての市政運営を担う市長として、改めて責任の重さに身の引き締まる思いでございます。
私は、幼少期を星野村で過ごし、美しい自然や様々な生き物と触れ合いながら、そして何よりも地域の皆様からの温かい愛情を受けながら育ちました。私にとって八女市は、ふるさとそのものであり、私自身の原点でございます。そして八女市に恩返しをしたい、市民の皆様が希望をもって暮らせる元気な八女市を創っていきたいと考えるようになりました。
その想いを実現するために、私は大学卒業後、経済産業省に入省し、国家公務員の視点から、様々な政策、政治について学びました。また、八女市の基幹産業たる農業の知見、そして国際感覚を身に着けるため、農業大国であるオランダでも研鑽を積んでまいりました。
私は今回の市長選挙を通じて、「変革」というキーワードを掲げてまいりました。
今なぜ変革が必要なのか。企業経営やビジネスの世界に、「ゆでがえる理論」というものがあります。カエルはいきなり熱いお湯に入れると、すぐにそこから逃げ出します。しかし冷たい水にいれて、少しずつその水温を上げていくと、温度の変化に慣れてしまい、逃げ出すタイミングを失って、最後は茹でガエルになってしまいます。
このように、ゆっくりと進む環境の変化や危機に対応する難しさ、そして気が付いた時には手遅れになってしまう恐ろしさを説明するのが、この理論ですが、今まさに八女市は手遅れになってしまうほんの一歩手前だと、そういう危機感を私は抱いております。
このままでは、多くの場所が、限界集落、さらには消滅集落になり、先人たちが長年紡いでこられた伝統、文化、技術が失われてしまう、そういった危機的な状況です。変革というものは、時に痛みも伴います。しかし、この変化の激しい、不確実な時代において、現状維持は衰退を意味します。八女市が直面するこの状況に真正面から立ち向かう、変化を恐れない政策を実行する、そんな市政を、市長としてリーダーシップを持って、実現してまいります。
また、変革に加えて、将来の八女市を創っていくための方針として、「八女を世界に」というテーマも訴えてまいりました。世界地図で見れば、八女市は小さな自治体かもしれませんが、私は海外を見てきたからこそ、この八女の様々な魅力、資源は、世界で勝負していけると確信しています。今八女市に足りていない要素の1つが何より発信力です。知ってもらえさえすれば、ここにはもっと人やお金が集まってきます。日本全体の経済が縮小しているからこそ、国内だけでなく、世界を見据えて勝負していく、そういった取組が必要です。
この変革の実現と世界への発信は一朝一夕で実現できるものではなく、1つ1つの政策を積み上げていくことが不可欠です。その政策の柱を8つに分けてご説明させていただきます。
まず、1点目は「市民が主役の市政を行う八女市」、この実現に向けた、市政改革でございます。
政治は市民のためのものです。市民の皆様に、政治をじぶんごととして考えていただけるように、市政に参画していただけるための仕組みを整えていきます。
具体的な取組として、まず市民の皆様との対話の機会を充実させてまいります。
この広い八女市において、すみずみまで声を聞くため、自らが各支所に出向き、支所職員や地域の方々と対話をする「移動市長室」を定期的に開設いたします。また、支所以外にも、八女市内の行政区長会をはじめとした地域の各種団体との座談会を定期的に開催するなど、現場の声に常に耳を傾ける「会いに行ける」、そして「会いに行く」市長を目指します。
また、ただ市民の皆様のお話をお伺いするだけではなく、実際に市民の方が政策提言をできる機会を充実させ、市民の声が政策に取り入れられる仕組みを整えてまいります。例えば、八女市こども議会を発展させるなど、幅広い世代が実際に政策提言をできる環境を整える他、官民合同の政策ワークショップなど、市の総合計画をはじめとした重要政策の策定に、市民の皆様が直接参加できる仕組みを充実させてまいります。
加えて、市政改革のためには、市役所内部が発展していくことも重要であり、市職員の皆さんが、その能力や創造性を最大限発揮できる環境作りにも取り組んでまいります。市長として、これからリーダーシップを持って様々な課題に挑戦してまいる覚悟ですが、市職員の協力なしには、円滑な市政運営は行えません。職員一人一人との対話を行っていくことはもちろん、外部人材の積極登用や、職員の自己研鑽のための機会を充実させ、市役所全体のレベルアップを図ってまいります。
また、所属部署の職責にとらわれず、八女市の発展のために、職員自らが自由に政策を策定し、実行できる制度を構築します。こうした取組を通して、すべての職員が、働きやすく、最大限の能力や創造性を発揮できる環境を整えます。
続いて2点目は、「全ての産業が元気で稼げる八女市」、これを実現するための、経済・産業政策でございます。経済産業省や海外で培った経験とネットワークを最大限活用し、市民の皆様のより豊かな生活の実現に取り組みます。この「豊かさ」という言葉の中には様々な要素がございますが、その中で、経済的豊かさ、これを私は実直に追及してまいります。
今、農林業や伝統工芸をはじめとして、八女の多くの産業が苦しい状況にあります。
日々、汗水たらして働かれておられる市民の皆様の努力が、収益の増加、手取りの増加という形で正当に、そして目に見える形で報われる、そういった経済の実現を目指します。また、市役所自身の財政状況も改善しなければいけません。八女市の経済が潤うことで、市役所の税収、自主財源も増加する、そういった絵姿を中長期的な視点で示してまいります。
具体的な取組として、まず農業分野においては、「食」を通じた八女ブランドの更なる価値向上と農産物の輸出拡大に取り組んでまいります。
八女茶をはじめとした八女の農産物の魅力を、JAをはじめとした関係団体とも協力しながら国内外に強く発信し、八女産農産物の更なる知名度の向上と消費拡大、そしてその結果としての価格向上を図ります。
同時に、有機栽培の推進や関連した認証の取得、海外の販路の確保などに取り組むことで、八女産農産物の輸出拡大を進めてまいります。
また、足元の課題への対応として、農業の生産性向上と耕作放棄地の有効活用に取り組むことも重要です。八女の伝統的な農業技術とスマート農業をはじめとした国内外の最新の技術を組み合わせることで、八女の様々な農作物の生産性向上を目指します。一方で、特に山間部に集中する、集約化や最新の農業技術の活用が難しいような農地については、新たな高付加価値作物の導入や、兼業農家・週末農家の誘致といった取組によって、耕作放棄地の再生・地域の活性化を進めてまいります。
あわせて稼げる林業の実現にも取り組んでまいります。林業をより稼げる産業に進化させるため、集約化、効率化などの取組をさらに推進するとともに、CLTなど新たな木質材料の活用も通じて、林業の収益性を向上させます。また、木材の生産のみならず、CO2の吸収量を販売することにより利益をあげる「カーボンクレジット」の活用によって、木の育成途中でも利益をあげられる林業の仕組みを確立し、八女を現代林業の先進地とすることを目指します。
また、農林業のみならず、商工・地場産業の活性化にも取り組んでまいります。商工業者の経営基盤強化や事業承継支援に加え、新規創業支援も拡大し、官民合同でのビジネスコンテストの開催など、新しい取組にも積極的に取り組んでまいります。
農林業や商工業といった地場産業の発展が私の考える経済・産業政策の基本ですが、高い付加価値を生み出す企業の誘致も同時に進めてまいります。その際、誘致企業が地場産業の発展に寄与するよう、また、誘致企業の撤退によって産業が空洞化しないよう、農林業関連や環境関連企業など、八女ならではの企業誘致に注力し、最終的に八女の強みを活かした産業集積の実現を目指します。
続いて3点目は、「教育や育児のための最高の環境が整った八女市」、これを実現するための子ども政策でございます。子どもたちは将来の八女市を担うかけがえのない宝であり、中長期的な八女の発展のためには、将来を担う子ども達への投資は不可欠です。充実した教育制度や手厚い育児支援を通して、輝かしい未来を担う人材への投資を進めてまいります。
具体的な取組として、まず、実質的な待機児童0の達成と山間部の保育所の活性化に取り組んでまいります。旧町村の保育所は児童数が減少する一方で、八女市の一部では児童数の増加により、希望の保育所に通わせることができないという保護者の方もいらっしゃいます。児童数が増加している地域にある既存の保育所の収容能力を向上させるとともに、居住地域以外の保育所にも通える環境を一層整備し、待機児童0を達成するとともに、山間部の保育所の活性化を目指します。
また、経済的な子育て負担の軽減にも当然取り組んでまいります。物価上昇が続く中で、子育てのための経済的負担を少しでも軽減することが、出生数の増加や、ファミリー層の移住増加に繋がります。政府の子育て政策の今後の方向性も踏まえながら、将来世代に負担を残さない形の財源を確保した上で、最大限子育て世代の負担軽減に取り組んでまいります。
あわせて、教育のデジタル化、教育DXの推進にも力を入れてまいります。地域ごとに生徒数の大きく異なる八女市内の小中学校で、均一かつより質の高い教育を提供するためには、教育のデジタル化、効率化が不可欠です。学校の通信環境の整備やタブレット端末等の学習ツールの普及に加えて、教職員等の研修を充実させるなど、ハード・ソフト両面から教育DX推進のための支援を行い、学校ごと、生徒ごとに、きめ細かい教育環境を提供してまいります。
続いて、4点目は、「医療・福祉が充実した八女市」、これを実現するための医療政策、福祉政策でございます。市民の皆様が健康な生活を送るためには、充実した医療・福祉制度が不可欠です。平坦部から山間部まで広い面積を有し、また高齢化が進む中においても、市民の皆様全員が安心して医療・福祉の恩恵を受けることができる街づくりを目指してまいります。
まず取り組むべきは、公立八女総合病院に関する議論の進展です。現在、公立八女総合病院の移転・建て替えに関する議論が進められていますが、何より重要なことは、医師の確保です。医師派遣を行う久留米大学医学部と十分に協議し、十分な医師数を確保するための公立病院のあり方に関する議論を加速させます。
また、筑後地域の広域的な医療体制のあり方について、広川町、筑後市等の近隣自治体ともよく協議するとともに、その意思決定過程を透明化させるため、市民の皆様に向けた説明会や意見交換会の場を各地域で定期的に設けることで、しっかりと市民の皆様に議論の経過をご説明してまいります。
また、高齢化が進む八女市においては、介護の負担軽減や認知症対策は喫緊の課題であり、現役世代が仕事や日々の生活に集中できる環境を整えることが重要です。介護スタッフや、家族介護者への支援、認知症の早期発見をさらに推進するとともに、農福連携も推進してまいります。農福連携とは、障がいを持つ方や高齢者が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組です。農福連携に取り組むことで、障がいを持つ方や高齢者にとってやりがいある就業の場を生み出すとともに、人手不足をはじめとした八女の農業の課題の解決に繋げてまいります。
5点目は、「誰もが安心・安全に住める八女市」、これを実現するための政策でございます。県内第2位の広大な面積を有する八女市において、どこの地域においても、誰もが安心・安全に暮らせるまちづくりを進めてまいります。
この安心・安全には様々な要素がございますが、まず第一に、防災・減災対策をさらに強化してまいります。災害を未然に防ぐことはもちろんのこと、災害は避けられないものとして対策を講じることも重要です。現状の流域治水対策や地震対策を見直すとともに、AIを活用した道路・河川状況の監視や、ドローンによる孤立集落への物資輸送など、民間企業とも協力しながら、最新技術を取り入れた防災対策を推進してまいります。
また、安心・安全の要素として、移動手段の確保が重要であり、その方策の1つとして、ライドシェアを推進してまいります。一般ドライバーが自家用車で乗客を有償で運ぶ「ライドシェア」の取組が今般、全国的に進んでおり、交通空白地解消のため、自治体などが主体となって行う「公共ライドシェア」の仕組みも整備されております。面積が広く、また高齢ドライバーが増加する八女市において、ライドシェアの普及は地域の移動手段の充実に不可欠だと考えております。人材・事業者支援や周辺自治体との連携等、早急にライドシェア普及に向けた取組を進め、最終的に市内全域での導入を目指してまいります。
6点目は、「伝統・文化・芸術が盛える八女市」、これを実現するための文化政策であります。八女は様々な伝統や文化が根付いており、これまで多くの芸術家も輩出してきました。こういった八女の文化資源を守り、さらに発展させるための取組を行ってまいります。
まず、伝統工芸産業のさらなる発展に取り組んでまいります。伝統工芸を産業としてさらに発展させていくため、仏壇や提灯、和紙といった伝統工芸品の国内外への販路拡大のための支援策をさらに充実させます。また、既存の伝統的な製品に加えて、伝統工芸技術を活用した新たな特産品創出を後押しすることで、新たな顧客獲得と伝統工芸産業の収益性の向上を目指します。
また、産業としてだけではなく、「文化」や「芸術」としての伝統工芸の位置付けを確立することで、八女の伝統工芸のさらなる認知度や価値の向上を目指します。文化発信の拠点として、この新庁舎も大いに活用してまいります。
また、伝統ある街並みの保全・活性化にも取り組んでまいります。福島や黒木町といった伝統的な街並みの保全事業をさらに充実させるとともに、空き家の利活用や新規創業を推進し、伝統建築や街並みを活用した中心市街地のさらなる活性化を目指します。その際、補助金ありきではなく、住民の経済社会活動を通じた街並み保全が進むよう、文化活動と経済活動が両立する街づくりを、官民一体となって推進します。
7点目は、「多くの人が訪れる八女市」、これを実現するための観光政策、人口減対策でございます。八女市には様々な観光資源がございます。この強みを活かして、八女市の魅力を積極的に発信し、移住者及び交流人口の増加を目指してまいります。
具体的な取組として、国内からの観光客はもちろん、インバウンド、外国人観光客の呼び込みにさらに力を入れてまいりたいと思います。新型コロナ感染症も落ち着き、再び増加したインバウンドを積極的に八女に呼び込んでまいります。外国人向けのPR・広報活動を充実させるとともに、市HPの多言語対応やインバウンド受入対応のための事業者支援を充実させてまいります。
同時に、空き家や廃校などの公共施設の再生・活用も進めてまいります。新型コロナ感染症の拡大を契機に、テレワーク需要が拡大し、会社所在地とは異なる場所で生活しながら仕事をする方の数が増えております。空き家を移住者の生活・活動拠点として整備するとともに、廃校などの公共施設をシェアオフィスや共同の作業場、芸術活動の拠点などとして使えるように改装・整備し、定住人口・交流人口の増加を図ってまいります。
また、観光面、経済面での、近隣自治体との連携も強化してまいります。八女市内はもちろん、筑後地域は様々な観光資源があり、県内の観光客数もパンデミック後、回復・増加傾向にあります。また、筑後圏は、福岡都市圏、熊本、大分とも近く、そうした九州の地理的中心に位置する利点も活かしていく必要がございます。鉄道が通っていない、福岡都市圏からの距離が遠いといった、八女市の弱点を補うためにも、近隣自治体との連携を進め、筑後地域が九州の観光や経済の拠点となる「筑後観光経済圏」の形成を目指し、八女市が主導して近隣自治体との議論を進めてまいります。
最後に8点目は、「環境先進都市八女」、これを実現するための環境政策であります。地球温暖化対策や循環型社会の形成の重要性が日に日に高まっている中、豊かな自然に恵まれた八女市だからこそ、環境政策に積極的に取り組み、日本を代表する環境先進都市に進化させてまいります。
まず第一に、カーボンニュートラル、脱炭素に向けた取組を強力に推進してまいります。二酸化炭素の排出を実質0にする、カーボンニュートラルの取組が世界中で求められています。八女市として、自治体単位でのカーボンニュートラル実現を目指す「ゼロカーボンシティ」の表明をいち早く行い、森林吸収源の確保や太陽光、バイオマスをはじめとした再生可能エネルギーの活用など、積極的に二酸化炭素排出削減の取組を推進することで、八女の農林業やエネルギー産業の発展、新産業の創出、地域の災害対応力強化につなげてまいります。
また、農地や林地の多面的価値の評価を推進してまいります。山間部の農地や林地は、農作物や木材の生産のみならず、地下水の涵養や生物多様性の維持等、様々な機能があります。農林業による収益だけではなく、そういった多面的機能を適切に評価することで、八女の環境維持のために必要な農林地の保全を後押ししてまいります。
以上、私の政策の基本的な考えの一端を申し上げましたが、その多くが、一筋縄にはいかない、実現には様々なハードルがある政策だと認識しておりますし、また、私一人でできることは限られております。まずは市職員そして市議の皆様との対話の積み重ねにより信頼関係を構築し、今後の市政について十分な議論を行ってまいります。そして、自らが各地域に直接出向くことにより、市民の皆様お一人お一人との対話を大切にしながら、市民が主役の、そして市民目線の開かれた市政を実現してまいります。時代の潮流を読み、新たな取組も恐れず果敢に挑戦していきながら、私の政治信条である「会いに行ける市長」、「会いに行く市長」として、全身全霊で市政の運営に邁進してまいる所存でございます。
議員各位におかれましても、より一層のご理解とご協力を賜りますことを切にお願い申し上げ、私の所信表明といたします。
長くなってしまいましたが、本日は貴重なお時間を拝借いたしましたこと、深く御礼申し上げます。改めまして、これからどうぞよろしくお願い申し上げます。
八女市長 簑原 悠太朗
この記事に関するお問い合わせ先
未来創造戦略室 秘書係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1109
ファックス:0943-24-8083
お問い合わせはこちら