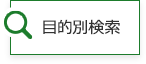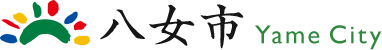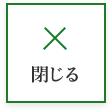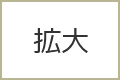令和7年度「八女市の学校教育」における教育指導課の主な施策等 および 令和7年度全国学力・学習状況調査結果
令和7年度「八女市の学校教育」における教育指導課の主な施策
教育指導課では、「令和7年度八女市の学校教育」に基づいて、各学校の学校経営・運営を支える次の施策を進めています。
○教務係(指導班)
・教育指導計画を基にした学校経営、校務運営、教育課程編成等への具体的な指導・支援
・非認知的能力についての分析及び学力層に着目した学力の実態分析を基にした学力向上プランの作成と実施・評価に対する指導・支援
・課題対応訪問等による各学校の実態に応じた具体的な指導・支援 等
○教育研究所
・学習指導の力量向上と職務遂行能力の育成を図る研修事業
・八女市の教育課題の解決及び指導方法改善を図る調査研究事業 等
○教育相談室・教育支援センター「あしたば」
・教育サポートセンターとしての機能充実
・「あしたば」通所生への学習支援及び社会的自立支援の充実
・いじめや不登校等に関する教育相談活動の充実 等
○特別支援教育室
・学校組織及び教職員の特別支援教育力の向上
・保護者等への相談支援の充実 等
八女市が育成を目指す資質・能力
八女市立学校では、「学びに向かう力・人間性等(非認知的能力)」の育成を重点としています。「学びに向かう力・人間性等(非認知的能力)」は、児童生徒が「どのように社会や世界と関わり、よりよい人生を送るか」に関わるものです。全国学力・学習状況調査の結果と八女市版非認知的能力アンケートの結果から、状況を分析します。
教科の「知識及び技能」や「思考力、判断力、表現力等」とともに、「学びに向かう力、人間性等(非認知的能力)」の三つの柱をバランスよく育成することを目指しています。
令和7年度全国学力・学習状況調査結果をお知らせします
令和7年度全国学力・学習状況調査における八女市の結果をお知らせします。この調査の目的は、全国の児童生徒一人一人の学習状況を把握、分析し、課題の改善や指導に役立てることにあります。
分析結果をもとに成果や課題を明らかにし、課題解決に向けて、指導方法の見直しや授業改善等の取組を行います。
八女市の全国学力・学習状況調査結果の概要
1 調査の対象
〇小学校6年生・義務教育学校6年生(以下小学生)
〇中学校3年生・義務教育学校9年生(以下中学生)
2 調査内容
○教科 国語、算数・数学、理科(中学校理科はオンライン方式での実施)
○児童生徒質問調査
※本調査によって測定できるのは、学力の一部であることに留意してください。
3 調査実施日
令和7年4月17日(木曜日)
※中学校理科は、4月14日~17日のうち1日
4 調査結果の概要
(1)教科に関する調査結果の概要
<小学生(14校)>
国語・理科は、全国・福岡県をやや上回りました。算数は、全国平均並みで、平均正答数の全国との差は0.1問(全16問)です。
<中学生(10校)>
国語・数学ともに、全国、福岡県を下回りました。平均正答数の全国との差は、国語は0.4問(全14問)、数学は0.7問(全15問)です。オンライン方式で実施された理科は、500を基準とするスコアで、全国503に対し八女市は475でした。
(2)児童生徒質問調査結果の概要
学力調査と合わせて、生活習慣や学習への取組などについての調査が実施されました(小学生71項目、中学生70項目)。質問調査のため、「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」を肯定的な回答として集計し、分析しています。子どもの学力は学校の授業だけでなく、基本的生活習慣や生活環境にも大きく左右されることが分かっています。結果の一部を紹介します。
○学校での生活や学習の様子
・93~94%の子どもが「友達関係に満足している」と思いながら学校生活を送っています。
・76~78%の子どもが「困りごとや不安がある時に、先生や学校にいる大人にいつでも相談できる」と思いながら学校生活を送っています。
・77~92%の子どもが「国語や算数・数学で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つ」という思いをもち、学習に取り組んでいます。
○学びに向かう力・人間性等(非認知的能力)に関わる結果
・「肯定的な回答が80%を超えている」または「全国平均を上回っている」項目は、次のとおりです。

・課題は、小学生、中学生ともに、学びを調整する力の「授業で、自分の考えを発表する機会では、自分の考えがうまく伝わるよう、資料や文章、話の組立てなどを工夫して発表する」ことです。この項目の肯定的回答は60%程です。指導の改善を図る必要があります。
※「学びに向かう力・人間性等(非認知的能力)」は、福岡県教育委員会の資料を基に、以下のように定義しています。
・学習方略とは、学習をより効果的に進めるための方法や工夫のことです。
・メタ認知とは、自分の思考や行動を客観的に把握し認識することです。
・自己有用感とは、自分と他者(集団や社会)との関係を自他共に肯定的に受け入れられることで生まれる、自己に対する肯定的な評価のことです。
・自己効力感とは、目の前にある目標を実現できる力をもてていると信じる感覚のことです。
○家庭での学習の様子
・普段(月曜日から金曜日)の1日当たりの家庭学習時間については、小学校6年生で1時間以上、中学校3年生で2時間以上取り組む子どもの割合が、全国平均を下回っています。自分の生活をふり返り、家庭学習、食事、休養及び睡眠等のリズムを整えること、学校からの課題(宿題)のほか、家で自分で計画を立てて家庭学習に取り組む習慣を身に付けることが必要です。
○生活習慣、生活全般
・約10%の子どもはきちんと朝食をとれていません。学習への影響も懸念されます。
5 今後の対策
学力調査結果や児童生徒質問調査結果を分析・考察し、「学びに向かう力・人間性等(非認知的能力)」の重点的な育成を図っていきます。また、個々の児童生徒の伸びや課題に着目し、教育活動の見直しや授業の改善を図っていきます。
<教育指導課において>
○学力向上の取組の充実や「学びに向かう力・人間性等(非認知的能力)」の育成等について、小・中学校等校長会と連携を図ります。
○「学びに向かう力・人間性等(非認知的能力)」の育成を重点とする学力向上を目指し、各学校に対し次の指導・支援を行います。
・「学びに向かう力・人間性等(非認知的能力)」の育成を重点とすることの周知徹底
・八女市版非認知的能力アンケートの実施と活用
・生徒指導の実践上の視点を明確にした学習指導
<各学校において>
○児童生徒質問調査の結果を分析・考察し、「学びに向かう力・人間性等(非認知的能力)」の状況を捉え、教育活動の見直しや授業の改善を図ります。
○教科に関する調査結果を基に、学力層(四分位)に着目した課題とその要因分析等を行い、学力向上の取組の改善を図ります。また、個々の児童生徒の伸びや課題に着目した実態分析を進めていきます。
○家庭と連携し、家庭生活において、学校からの課題(宿題)を含めた学習時間を確保し、食事・休養・睡眠等のリズムを整える取組を行っていきます。
6 ご家庭へのお願い
〇お子さんのよいところや伸びているところをほめ、努力が必要なところはアドバイスや励ましをお願いします。
〇ゲーム機やスマートフォン等の使い方や使う時間などについてお子さんと話し合ってルールを決め、家庭での時間を有意義に過ごせるようにしましょう。
〇学校からの課題(宿題)を含めた学習時間を確保し、食事・休養・睡眠等のリズムを整えるようにしましょう。
学校・家庭・地域それぞれの場での計画的・総合的な取組により、子どもの学力の伸びが期待できると考えます。今後ともご支援・ご協力をよろしくお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
教育指導課 教務係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9176
ファックス:0943-24-4331