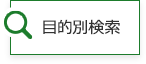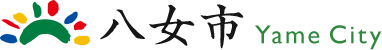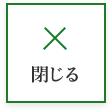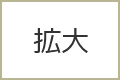介護サービスを利用したい
介護サービスを利用するには、要介護認定の申請をして「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。
対象者(介護保険のサービスを利用できる方)
(1)第1号被保険者(65歳以上の方)
原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な方。
(2)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方。
特定疾病については、以下に掲載している厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
【厚生労働省リーフレット】介護保険制度について(40歳になられた方へ)(PDFファイル:1.3MB)
介護サービス利用までの手順
1.「要介護認定」申請
八女市役所 介護長寿課 介護保険係もしくは各支所の介護保険担当窓口にて「要介護認定」の申請手続きをします。
申請は本人や家族のほか、居宅支援事業所(ケアプラン作成事業者)や、ご利用中の介護保険施設、地域包括支援センターなど依頼して、申請を代行してもらうこともできます。
また、郵送での提出も受け付けています。
申請に必要なもの
・介護保険被保険者証(黄色)(紛失等によりお手元にない場合もお手続き可能です)
・主治医の情報(病院名、医師名を申請書に記載いただきます)
マイナ保険証への移行に伴い、第2号保険者(40歳以上65歳未満)の医療保険被保険者証の提出は不要となります。
申請時に、マイナンバーを用いた情報照会等により医療保険の加入状況の確認を行いますので、お時間をいただく場合があります。
情報照会により加入状況が確認できなかった場合、後日「資格情報のお知らせ」等の写しをご提出いただきます。「資格情報のお知らせ」等とは、下記のいずれかです。
・従来の健康保険証(有効期間内のもの。最長で令和7年12月1日まで)
・医療保険者が発行する「資格確認のお知らせ」
・医療保険者が発行する「資格確認証」
・マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」
2.訪問調査と主治医意見書
訪問調査について
訪問調査では、八女市の職員のほか、八女市が委託する事業所の調査員が訪問し、心身の状況や生活の様子を本人や家族から聞き取ります。 調査の時間は、約1時間程度です。
申請いただいてから1~2週間ほどで、調査員が日程調整のお電話をしますので、ご対応をお願いします。
・八女市調査員「0943-23-1303」
・株式会社アール・ツーエス(訪問調査委託事業所)「092」「090」「080」「070」から始まる番号
県外にお住まいの方には、上記以外からお電話を差し上げる場合がありますので、ご了承ください。
訪問日は、平日(祝日以外の月~金まで)です。
調査の開始時刻は、10:00~11:00または13:00~14:00が基本です。
申請後に急な体調変化(発熱等)、入院があった場合、調査場所の変更があるときは、すみやかにご連絡ください。
主治医への連絡について
主治医に介護の申請をしたことを伝えてください。
主治医意見書作成のために受診が必要かどうかを確認してください。
認定申請後に、八女市から主治医に作成依頼をします。
主治医意見書とは
申請者の介護保険サービスの必要性について、かかりつけ医(主治医)が医学的な意見を記載し、介護認定審査会の資料として用いるものです。申請者が2号被保険者の場合、主治医意見書に基づき「特定疾病」に該当するかどうか判断します。
3.介護認定審査会
書類が揃ったら、調査結果及び主治医意見書の一部の項目をコンピューターに入力し、一次判定を行います。
その後、介護認定審査会が、一次判定の結果と調査員の特記事項、主治医意見書をもとに二次判定を行います。
介護認定審査会は、医療、保健、福祉の専門家で構成されています。
4.認定結果の通知
介護認定審査会の判定に基づき、「要介護状態区分」を認定します。
「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階に区分され、それに「自立」を合わせて合計8段階に分けられます。
原則、介護認定審査会の翌日に、認定結果通知・介護保険被保険者証を発送します。大切に保管してください。
認定結果は簡易書留で郵送しています。
有効期間満了後も介護サービスを利用するためには、期間内に更新申請を行い、再度認定を受ける必要があります。更新申請は、有効期間満了日の60日前から受け付けています。また、有効期間内に心身の状態が大きく変わった場合には、認定期間の満了を待たずに「区分変更申請」を行うことができます。
5.ケアプラン作成
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。
認定された介護状態区分に応じて、ケアプラン作成機関に連絡してください。
要介護1~5と判断された方
介護保険の対象者で、介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な方です。
・在宅のサービスを利用→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)がケアプランを作成します。
・施設のサービスを利用→施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。
【相談窓口】居宅支援事業所、施設(入所希望の場合)
要支援1,2と判断された方
介護保険の対象者で、比較的要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い方です。 地域包括支援センターの職員が心身の状況、環境等を勘案しながらケアプランを作成し、指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、関係機関との連絡調整を行ないます。
【相談窓口】地域包括支援センター
非該当(自立)と判断された方
介護保険サービスの対象者にはなりませんが、介護予防や健康づくりのための「一般介護予防事業」に参加することができます。 ただし、65歳以上の場合は基本チェックリストを受けて「事業対象者」と判定された場合は、「介護予防・日常生活支援総合事業」が利用できます。
【相談窓口】地域包括支援センター
6.介護サービス利用
介護サービス事業所でのサービスを利用します。日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。
平成29年4月から、要支援1・2の方が利用できる介護保険サービスのうち、「ホームヘルプ」と「デイサービス」が、介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。