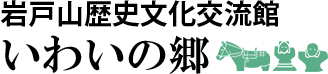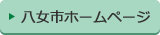5.磐井の戦い その後
5-1 筑紫君磐井以後の八女古墳群
『日本書紀』によれば、筑紫君磐井が敗戦した後、その息子の葛子(くずこ)は「糟屋屯倉(かすやのみやけ)」を献上して命乞いをしていることから、戦いの前には現在の福岡市付近までが筑紫君の勢力範囲であったことが窺えます。八女丘陵では岩戸山古墳の後も、乗場古墳(のりばこふん)・善蔵塚古墳(ぜんぞうづかこふん)・鶴見山古墳(つるみやまこふん)などの大型前方後円墳が築造され続けます。その中でも、鶴見山古墳では平成17年の調査で武装石人が出土し、筑紫君磐井の後も筑紫君一族の象徴とも言える石人・石馬が作られ続けていることが明らかとなりました。また、童男山古墳群でも「子負いの女性石人(こおいのじょせいせきじん:市指定文化財)」が発見されており、古墳時代を通して八女古墳群では石人・石馬が古墳に立てられていたことがわかります。
また、『日本書紀』天智10年の条には「筑紫君薩野馬(つくしのきみさちやま)」の名がみられ、磐井の戦いから約150年経過した後にも筑紫君一族が活躍していたことがわかります。
(ワンポイントメモ)
- 八女古墳群では岩戸山古墳に後続する古墳からも、「筑紫君」の象徴である石人を立てている古墳が見つかっています。また、「筑紫君」を名乗る人も文献に出てきます。磐井の戦いの後も、「筑紫君」は残っていたことがうかがえます。

鶴見山古墳(八女市豊福)

鶴見山古墳の石人(出土時)
郷土の英雄 「筑紫君磐井」
西暦527年~528年の磐井の戦いは、『日本書紀』の中では反逆者磐井を成敗した物語となっていますが、5世紀後半ころから大王を頂点とした統一国家を目指すヤマト王権と、九州の盟主たる筑紫君磐井が繰り広げた、最後の統一戦争だったのかもしれません。
筑紫君磐井は、九州の盟主としてヤマト王権からの介入を排し、八女地方はもちろんのこと、九州の人々が誇り高く豊かに生活が出来ることを望み、九州の人々のために戦った英雄だったのかもしれません。
この記事に関するお問い合わせ先
(文化振興課 歴史文化交流館係)
〒834-0006 福岡県八女市吉田1562番地1
電話番号:0943-24-3200
ファックス:0943-24-3210
お問い合わせはこちら