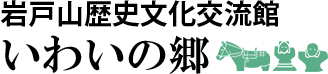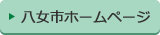4.岩戸山古墳が世界最多!「石人・石馬(石製表飾)」
ここでは、岩戸山古墳を代表する「石人・石馬」について説明します。
「石人・石馬」とは

石人・石馬
(岩戸山歴史文化交流館展示室内)
岩戸山古墳と言えば、何よりも「石人・石馬」です。古墳の表面には、粘土を焼いて作った「埴輪(はにわ)」を立てますが、岩戸山古墳では埴輪だけでなく阿蘇溶結凝灰岩(あそようけつぎょうかいがん)という石を削って作った「石人・石馬(せきじん・せきば)」が立てられています。
岩戸山古墳では、現在100を超える数の石人・石馬が発見されています。石製表飾が2番目に多い古墳は、熊本県八代郡氷川町の姫ノ城古墳(野津古墳群)の16個であることからも、岩戸山古墳の石人・石馬は他の古墳を圧倒する数です。
(ワンポイントメモ)
「石人・石馬」は、埴輪を石で作ったもので、筑後・熊本県北部を中心に分布しています。

靫(ゆぎ)を負う石人(岩戸山古墳)

武装石人(鶴見山古墳)

石盾(岩戸山古墳)

石馬(岩戸山古墳)
石人の材料「阿蘇溶結凝灰岩」
石人・石馬の材料は、約9万年前に阿蘇山が噴火した際の火砕流が固まってできた「阿蘇溶結凝灰岩」という石です。柔らかい石で加工しやすい特徴があり、伝統工芸品である八女石灯ろうや、八女市上陽町にある洗玉橋などの眼鏡橋や石垣の部材として使われています。
(ワンポイントメモ)
- 9万年前の阿蘇山の火砕流は、関門海峡を越えて山口県まで流れたと言われています。火砕流の後の八女市は、数10メートルの厚さで火砕流に覆われたようです。
- ちなみに、堅牢な熊本城の石垣も、石人・石馬と同じ阿蘇溶結凝灰岩で作られています。
石人・石馬(石製表飾)の分布
岩戸山古墳に特徴的な「石の埴輪」とも言える「石人・石馬(せきじん・せきば)」は、福岡県南部の筑後地方や熊本県北半部に数多く分布し、一部、佐賀県や大分県・宮崎県・鳥取県で発見されています。
なかでも、人の形をした「石人」がある古墳は、現在のところ熊本市(富ノ尾古墳)がいちばん南端になります。筑後や熊本県北部の「石人」の分布は、筑紫君勢力の中心的範囲を暗に示していると言えます。
また、『日本書紀』で筑紫君と連合して戦ったと言われる「火の国・豊の国」にも、石製表飾が点在し、石製品が16個見つかっている熊本県八代郡氷川町の「野津古墳群(のづこふんぐん)」は、「火の君(ひのきみ)」の本拠地と言われています。
このように、石人・石馬等の「磐井の乱」のストーリーと同じ状況が確認されます。
(ワンポイントメモ)
- 石人の分布から、磐井の頃の「筑紫君」の範囲の南端は、人の形の「石人」がいる、現在の熊本市付近までであった可能性が考えられます。

石人・石馬など石製表飾の分布(当館図録より)
この記事に関するお問い合わせ先
(文化振興課 歴史文化交流館係)
〒834-0006 福岡県八女市吉田1562番地1
電話番号:0943-24-3200
ファックス:0943-24-3210
お問い合わせはこちら