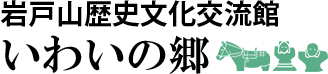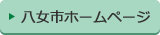2.筑紫君磐井の戦い(「筑紫君磐井の乱」)

岩戸山古墳(西上空から)
ここでは、奈良時代に作られた日本の歴史書「古事記(こじき)」・「日本書紀(にほんしょき)」や「筑後国風土記(ちくごのくにふどき)」に描かれている内容をもとに、「筑紫君磐井の戦い」について説明します。
(ワンポイントメモ)
- 現在、教科書では「筑紫国造磐井の乱」と書いてありますが、近年の研究では「筑紫君磐井」と表記され始めています。また、大王に背いた「乱(反乱)」というよりは古代の日本が国としてまとまっていく過程での「戦争」であったのではないかと考えられ始めています。
これらを踏まえて、このページでは「筑紫君磐井の戦い」と表記しています。
2-1 戦い前夜
当時の日本は、近畿地方を中心としたヤマトが、各地の豪族と連合して、緩やかな豪族連合を作っていました。これをヤマト王権(やまとおうけん)と呼びます。その象徴が、前方後円墳をはじめとする古墳の存在です。八女古墳群でも5世紀以降、ヤマト王権の象徴とも言える前方後円墳を作っていることから、八女を含む「筑紫君」は、ヤマト王権と友好関係にあったと考えられます。
当時の朝鮮半島は、高句麗(こうくり)・新羅(しらぎ)・百済(くだら)の3つの国に分かれて争っていました。筑紫君磐井の頃、ヤマト王権は継体大王(けいたいだいおう)がリーダーでした。ヤマト王権は百済と同盟関係でしたが、その頃の百済は高句麗との戦いに苦戦していました。
そこでヤマト王権は、同盟関係にあった百済を救援すべく、朝鮮半島に近江毛野(おうみのけぬ)の軍を送ろうとしていました。
(ワンポイントメモ)
- 日本はヤマト王権が各地の豪族と連合を作っていました。朝鮮半島では高句麗・新羅・百済が覇権を争っていました。
- ヤマト王権は百済と同盟関係にありました。
2-2 筑紫君のライバル‐ヤマト王権と継体大王‐
継体大王(けいたいだいおう)は男大迹王(をほどおう)という名前で『古事記』や『日本書紀』に登場します、応神天皇(おうじんてんのう)の子孫にあたるとされ、幼少期を近江(現在の滋賀県)で過ごし、越前(現在の福井県)で育ち、越前地方を統治していたようです。
西暦506年、ヤマト王権では武烈(ぶれつ)大王が跡継ぎを決めずに亡くなり、後継者問題が起こりました。ヤマト王権は跡継ぎを誰にするか議論を重ねた結果、男大迹王を跡継ぎ候補に決め、説得を重ねて男大迹王が大王を継ぐことになったようです。『日本書紀』では、西暦507年に58歳で大王を継いだことになっています。
その後、継体大王は約19年間は大和に入らず京都府南部(京田辺市・長岡京市)付近に宮を置き、筑紫君磐井との戦いの前年(526年)に奈良県桜井市の磐余玉穂宮(いわれたまほのみや)に入ったとされています。
継体大王の頃は、朝鮮半島が緊張している時期で、高句麗や新羅の脅威に対抗すべく、百済から援軍の要請が何度もありました。継体大王が百済の救援をする中で、西暦527年に「筑紫君磐井の戦い」が起こったのです。
大阪府高槻市にある今城塚古墳(いましろづかこふん:全長約180m)は発掘調査の成果から、継体大王が造った古墳とされています。
(ワンポイントメモ)
- 宮内庁の陵墓(りょうぼ)になっている継体天皇のお墓は、大阪府茨木市(いばらきし)の大田茶臼山古墳(おおたちゃうすやまこふん)ですが、発掘調査の成果から継体大王の真のお墓は今城塚古墳であると考えられています。
- 今城塚古墳ではピンク色をした石棺の破片が見つかっていて、はるばる熊本県宇土市(うとし)から運んばれたことが分かっています。岩戸山古墳の「石人・石馬」と同じ、阿蘇の溶結凝灰岩(ようけつぎょうかいがん)で作られています。
- 今城塚古墳について、今城塚古代歴史館(いましろ大王の杜)で知ることができます
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/history/list8.html)

継体大王の陵墓とされる今城塚古墳
(大阪府高槻市) ※高槻市提供

今城塚古墳の埴輪たち
(復元展示)※高槻市提供
2-3 ヤマト王権VS筑紫連合 勃発!
『日本書紀』によれば、筑紫君磐井は新羅から賄賂を貰い、ヤマト王権の百済救援軍が朝鮮半島に向かうことを阻止しています。
これにより、ヤマト王権(継体大王)と筑紫連合(筑紫・豊・火)の「戦争」がはじまります。
筑紫・豊・火の連合軍(磐井)とヤマト王権(継体大王)との戦いは西暦527年に始まり、翌年には筑紫君磐井は、継体大王が派遣した物部麁鹿火(もののべのあらかひ)と御井(みい:現在の久留米市)で交戦します。
2-4 磐井、敗北する
激戦の末、戦いはヤマト王権(継体大王)の勝利に終わります。
『古事記』『日本書紀』では、筑紫君磐井は戦闘中に斬り殺されたことになっています。一方、『筑後国風土記(逸文)』では、磐井は豊の国に逃げて山中で絶命したとされます。磐井は戦いで殺されたのか、逃げたのかは不明です。
『日本書紀』によれば、戦いのあと、磐井の息子「葛子(くずこ)」は、糟屋屯倉(かすやのみやけ)を差し出して命乞いをしています。このことから、戦いの前の筑紫君の勢力は、現在の糟屋郡(福岡市付近)まであったことが分かります。
近年の研究では、「筑紫君磐井の乱」は磐井がヤマト王権に対して行った反乱ということではなく、筑紫地域をはじめとする人民を守るための戦いであったという考えも提唱されはじめ、飛鳥・奈良時代に向けて、国家が形成されていく過程での「古代の統一戦争」であったとする見解もあります。
2-5 古墳時代の九州の英雄 「筑紫君磐井」
日本の歴史書である『古事記(こじき)』『日本書紀(にほんしょき)』では、「火の国」「豊の国」と連合してヤマト王権と戦った筑紫君磐井は、天皇の命令に従わない悪者として描かれています。
歴史書では反逆者として描かれる「磐井」ですが、九州北部を取りまとめ、岩戸山古墳のような大きな古墳はひとりで作れるものではなく、多くの人々の協力が必要です。この点からも、「筑紫君磐井」は、地域の人々にすごく慕われた、立派なリーダーであったことがわかります。
この記事に関するお問い合わせ先
(文化振興課 歴史文化交流館係)
〒834-0006 福岡県八女市吉田1562番地1
電話番号:0943-24-3200
ファックス:0943-24-3210
お問い合わせはこちら